*今までの文芸誌の表紙*
創刊号から第5号まで 第6号から10号まで 第11号から
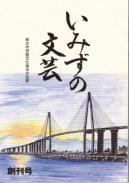
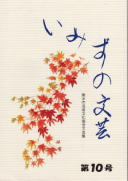
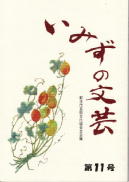
令和6年度の活動状況
● いみずの文芸 第12号 令和6年11月1日発刊いたしました。
※ 射水市芸術文化協会文芸部員の短歌・詩・俳句・漢詩・川柳・などの作品多数収録されています。射水市の図書館、各コミュニティセンター、市の各庁舎などで閲覧できます。是非手に取ってご覧ください。
・川柳 ・・・・・
川柳は、俳句と同じ 「俳諧の連歌」から生まれた文芸で、五七五の十七音からなる身近な文芸です。 俳句は、自然や四季の移ろいを詩情豊かに詠むのに対し、川柳は人やその心等の人間模様を親しみやすい口語体で詠みます。 「大門川柳の会」 は平成12年4月川柳に興味・関心をもった仲間数人で設立しました。この文集では、会員自薦の自信句各8句を掲句しています。
・漢詩 ・・・・・
漢詩は中国で生まれ、中華文明の伝来に伴い、日本でも作られるようになりました。一句 が四言、五言、または七言からなるのが普通です。射水市で漢詩に取り組んでおられる方はごく稀で、個人の活動が中心です。 祝い事や各種の行事を漢字に託し詩を作り、吟ずるなどの活動をしています。また市の中央図書館での 「漢詩に親しむ会」 においても、過去の偉人漢詩や自らの作品を披講し、詩の作り方や観賞の面白さを解くなどの活動にも努めています。
・俳句 ・・・・・
俳句は、古来身近な文芸として親しまれてきました。自然との関わりが深くなり親しくなることが、俳句の最初の喜びです。それぞれが感じたことを五七五の調べに乗せて句を作りますが最初は上手な表現といかないまでも、繰り返し挑戦するうちに適切な言葉、句にふさわしい言い回しが見つかるようになります。この「いみずの文芸」第4集では、「萌芽俳句会」 「菱水吟社」の会員の自薦の句を各8句掲載しました。
・短歌 ・・・・・
射水市には、昭和55年に松本福督師によって 「短歌の創作、披講、相互批評により結社を超えて研鑽を重ね、人間形成にも努める」ことを目指し、「新湊短歌会」が創設されました。また 「いみずの文芸」の発刊を機に、従来からいろいろな結社やグループ、あるいは個人で短歌に親しんでいた仲間で 「みしまの短歌会」 が結社されました。この文集には、二つの短歌会会員12名の自薦作、各8首を掲載しました。
・前句 ・・・・・
前句は室町時代に俳諧の連歌から分離独立し、江戸時代に隆盛した「前句付」が原点と言われています。それが加賀藩の金沢から射水・高岡・砺波方面に波及し、越中の地で特に発展を遂げた文芸です。 「大島前句会」 は、この歴史ある文芸に興味・関心をもった人間が集い、平成9年に旗揚げしました。 以後毎月1回例会を開き、和やかに研鑽を重ねています。 本号では前句の作り方を解説し、会員自薦の秀句を各種ごとに2句掲載しています。